畏
音読みは、「イ」。訓読みは、「おそーれる、かしこーい、かしこーまる」。
この漢字の上部は、稲(いね)を育てる土地の「田」のように見えるが、そうではなく、鬼(おに)の頭らしい。
そこで、確認のため、「鬼」の古い字形をみてみると、

確かに頭を「田」のように書いてあって、鬼が跪(ひざまず)いているような姿。
一方、「畏」は、

と描かれていて、鬼が手に何か持っているように見える。
辞書によって解釈は異なるが、共通しているのは、鬼が手に何か棒状の物を持っている形である、ということ。その棒状のものは、鞭(むち)や何らかの武器、『字統』では、古い時代の聖職者が持つ杖(つえ)のような形をしたもの、としている。
「田」が鬼の頭?、と、不思議に思えるが、ここでいう鬼は、桃太郎や節分、鬼滅の刃、などに登場する鬼とは異なり、亡くなった人の魂(たましい)で姿は見えないことから、漢字で表す場合、漠然としたイメージで書くしかなかったのではないかと思う。
では、「畏」の下の部分はなぜこのような形になったのか?
例えば、
止
は、足の形。最後の一画はまっすぐな横線になっているが、
足
は、「口+止」ではなく、最後の一画を止めずに払ったようになっている。そして、
長*長い髪の人(老人。長老)の形。
は、止や足の最後の二画を、先に「レ」のように一画で書いている。
「畏」の下の部分も「長」と同じように字形が変化したためだと思う。
手に持っていた棒状のものはどこへ?と疑問は残るが、これに関してはよくわからない。省略されたのか、あるいは、畏の下の部分の最初の一画がその棒状のものに相当するのか・・・。
成り立ちについてはこのぐらいにして、
改めて、「畏」の意味について、『漢字源』をみてみた。
①おさえられた感じを受ける。威圧を感じて心がすくむ。
また、おそろしくて気味が悪い。おびえる。
②こわい目にあう。また、おどされる。たちすくむ。
③気味悪さ。また、威圧を受けた感じ。
④心のすくむようなさま。こわいさま。転じて、尊敬すべき。
[日本]
①おそれ多い。また、ありがたい。
②おそれ入ってつつしむ。また、つつしんで承る。
こうして、意味をみてみると、目に見えない、姿が見えない存在を、
・恐い!と感じて、恐れたり、怯(おび)える
・更には、威圧感を感じる
といったマイナスイメージから、そういった存在に対して、
・敬(うやま)う
・更には、ありがたく思う
というようなプラスのイメージへと意味が派生していったのではないかと思う。
普段、あまり目にしない漢字のような気もするが、命令や依頼などを謹(つつし)んでお受けします、承(うけたまわ)りました、と言うときに、
かしこまりました
と言うこともあって、漢字で書くと、
畏まりました
う~ん、やっぱり、ひらがなで書くなあ<笑>
熟語に関しては、ひとつだけ気になったものがあった。
畏日(イジツ)
意味は、「光の強い真夏の太陽のこと。また夏の日。」
これは、次のような故事によるとのこと。
中国、晋(シン)の趙衰(チョウシ)と趙盾(チョウトン)の人物評を求められた賈季(カキ)が「趙衰は冬の太陽で、趙盾は夏の太陽です」と答えたという『春秋左氏伝』の文に、晋の杜預(トヨ)が「冬日愛すべく、夏日畏(おそ)るべし」という注を付したことから。『漢字ペディア』より。下線部差し替え。
よって、畏日の対義語は、
愛日(アイジツ)
これは、「冬の日光、冬の日」という意味の他、
・時間を惜しむ。
・日時を惜しんで父母に孝養を尽くす
という意味もある。
これからいよいよ本格的な冬の到来。愛日の日々を送りたい(^_^)

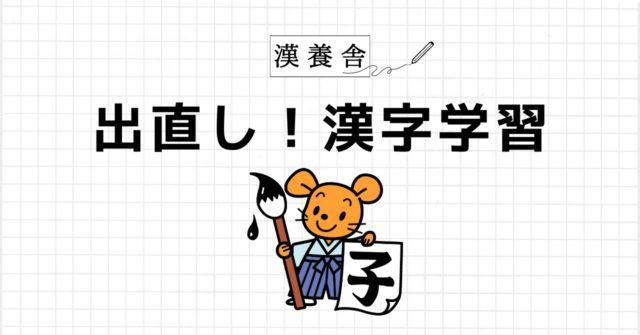
コメント